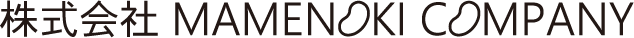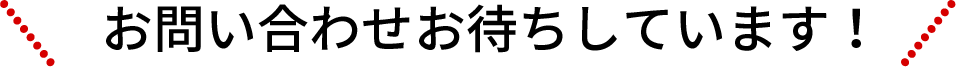2024年記事一覧
3.ポスティングで集客できるものだけお請けします。
大変恐れ入りますが、
せっかくお問い合わせをいただきましても
ポスティングについては当社からご依頼をお断りすることがございます。
お話を伺った上で、チラシの集客に不向きな商品であると感じた場合です。
少し長くなりますが、その理由をお話します。
ポスティングは素晴らしい広告ツールですが、残念ながら魔法の広告ではありません。
当然、ポスティングに向いている商品もあれば、不向きな商品もございます。
ポスティング広告はこちらから一方的にチラシを見せるプッシュ広告です。
興味がある方にも、そうでない方にもチラシをお届けすることができます。
これは、web広告には無い強みでもありますが、逆にターゲットが限られてしまう商品には
非常に不向きな広告ということになります。
例えば美容室のチラシの場合、女性である事が一番のターゲットになりますが
それ以外は年齢層・年収などは幅広く多くの方がターゲットになります。
ポスティングでの集客も比較的簡単で、ポスティングに向いている商品と言えます。
これが、ひな人形を販売するチラシの場合はどうでしょうか。
ひな人形のチラシに反応してもらうためには、
- 女の子のお子様がいる(または産まれる)
- お子様がひな人形を購入したい年齢である
- 親御様がお子様のためにひな人形を購入したいと思っている
ということが最低条件になり、女の子のお子様が居ない家庭や既にひな人形を購入されている家庭は完全にターゲット外になってしまいます。
ターゲットの牌が狭いということは、プッシュ広告では無駄撒きが発生する可能性が高いということになります。
そして更に最もハードルが高い部分が仮にターゲットにチラシが届いたとしても、チラシを見て、ひな人形を購入してくれる方がどの程度いらっしゃるかという部分です。
ひな人形を購入するシチュエーションとして最も多いのは・百貨店などの季節ごとの催事や人形専門店などへの来店ではないでしょうか。
そのような催しについては、まず、ネットで調べて来店するというのが自然な動きになってしまいます。
チラシでひな人形を宣伝されることになれていないというのも、反響を獲得できない要因です。
不特定多数の方にこちらから一方的にチラシを見せる
プッシュ広告だからこそ
- 出来る限りたくさんの方が
ターゲットになる - 大多数の方が知っている
商品(サービス)である
ことが、反響を獲得する上で重要に
なってまいります。
私たちはポスティングのプロとして、
いただいた貴重な販促費以上のリターンを
お返しできないと感じた場合や
ポスティング広告でお請けするべきではないと
感じたものについては
その理由をお伝えし、お断りしています。
ですが私たちがご提案できるのは
ポスティング広告だけではありません。
- ポスティングでは難しいですが、
DMなら可能性はあります! - その商品であればLPを制作して
webの広告で集客してはいかがでしょうか?
等、私たちが持っているノウハウを最大限に活かして提案をさせていただきますので
まずは、どんなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。
私たちは、お客様の利益に
貢献したい会社です!
この想いが伝われば、
大変嬉しく思います!
チラシに載せる写真はどんなものがいい?目に留まるチラシ作りのコツ
チラシの反響率を左右する要素のひとつに、写真選びがあります。チラシには興味がないのに、「何のチラシだろう?」と思わず見てしまった経験はないでしょうか?思わず目を引く写真とはどのようなものなのか、写真の選び方とチラシ作りのコツを解説します!
ポスティングチラシに写真は載せたほうがいい?
人に読んでもらえる魅力的なチラシとは、読みやすく、内容が伝わりやすいものであることが必須です。 人はチラシを手に取ってから、ほんの数秒でいる・いらないかを判断しています。そのためチラシを読んでもらうためには、思わず目を引くようなデザインや「何のチラシだろう?」と興味を引くような工夫が必要です。
写真を入れることによりチラシにインパクトをもたせることができるだけではなく、何のチラシなのかを瞬時に伝えることができます。また商品・サービスのメリットや効果なども視覚的に伝わりやすくなります。
一方で「ほかのチラシは写真ばかりのものが多いから、あえて文章だけのチラシにして目立たせよう」と思う方もいるかもしれません。
たしかに文字で埋め尽くされたチラシは、他のチラシと比較して目立つかもしれません。しかし目に留まったからと言って、チラシを読んでもらえるかは別問題です。
人はチラシを読むことに時間や労力を要するので、多少なりともストレスを感じます。そのため文字ばかりのチラシは内容がパッと見て分かりにくく、読み手の読む気力を失わせてしまうでしょう。
大切なのは、読み手にとって分かりやすいこと。写真を有効活用することでストレスなく読め、興味関心を引く魅力的なチラシになるでしょう。
ポスティングチラシにはどんな写真を載せたらいい?
写真を載せることでチラシが読みやすくなることは先述しましたが、いざチラシを作るときはどんな写真を選べばよいのでしょうか。
人の顔写真を載せる
人の顔写真は、人の関心を引きやすくなるのでおすすめです。人は本能的に、人間の顔に関心がいく習性があります。そのためイラストやマネキンの写真よりも、本物の人の顔写真を使用したほうが反響率は高くなります。
例えばフィットネスジムや美容院のチラシなど、爽やかな人の写真を取り入れることで、生き生きとし活気にあふれた印象を与えることができます。
またチラシにお店の店長やスタッフの顔写真を載せることで、お客さんに親近感を持ってもらいやすいというメリットもあります。
初めて行くお店や初めて利用するサービスでは、一般的にお客さんは緊張や不安を感じやすくなります。直接体を触られる整体や、依頼してみないと結果が分からない外壁塗装など、「事前にどんな雰囲気なのか知りたい」「人を見てお願いするかどうかを決めたい」と感じる人も少なくありません。
そんなときにチラシに店長やスタッフなどの顔写真があることで雰囲気や人柄が伝わりやすくなり、信頼感を持ってもらいやすくなります。
before・afterの写真を載せる
エステや化粧品、ダイエット商品などのチラシでは、before・afterの写真を載せることで反響率がアップします。before・afterの写真があることでどのように変化するのかを視覚的に訴えやすく、商品の効果やメリットをより具体的に伝えることができます。 特に自分に近い年齢や悩みを持っている人の写真には共感しやすいので、before・afterの写真は「自分もこうなれるのかな?」とお客さんの興味関心を引きやすくなるでしょう。
チラシの反響率を上げる写真の 載せ方
せっかくよい写真を使用していても、写真の載せ方によっては読まれないチラシになってしまうこともあります。チラシの反響率を上げるにはどうしたらよいのか、写真の載せ方をご紹介します。
写真の周りには余白を残す
たくさんの写真をギュウギュウに載せてしまうと、窮屈感があり読みたいという気持ちを低減させてしまいます。写真の周りにはほどよく余白を作るなどして、写真が活きる読みやすいデザインを意識しましょう。
画像のサイズや端をそろえる
写真を並べて載せる際は、写真のサイズや端を揃えることを意識しましょう。写真のサイズがバラバラであったり端が揃っておらずガタガタだったりすると、読み手に違和感を与えます。写真のサイズや端が揃っているだけでスッキリとした印象になり、読みやすいチラシになるでしょう。
写真に説明文を加える
写真に添えられた短い説明文やコメントのことを、キャプションといいます。人は写真に添えられた文章も一緒に読む習性があるため、キャプションをつけることでより写真の意図が伝わりやすくなり、印象を強める効果があります。写真の説明を一言付けたり、顧客の口コミなどを添えたりすることで、より興味を引く魅力的なチラシになるでしょう。
写真はプロに頼んだ方がいい?
チラシに載せるチラシは、可能であればプロに頼んだほうが間違いはないでしょう。被写体との構図やピントのぼかし方、モデルへのポーズの指示など、やはりプロならではのクオリティがあります。
しかし予算の都合などからプロのカメラマンに依頼をすることが難しい場合は、必ずしもプロが撮ったものでなくても大丈夫です。
最近はスマホのカメラでもクオリティの高い写真が撮れる機能が備わっており、初心者でも扱いやすい一眼レフカメラもあります。
また仮に撮った写真が満足のいく仕上がりにならなかったとしても、後からレタッチ(画像編集)することも可能。明るさの調整や色味の補正、トリミングなど、初心者でも簡単にできます。
チラシの配布規模が大きく、力の入ったものにしたい場合はプロに任せると安心ですが、配布規模が小さく地域密着型の場合などは、自分たちで撮った写真のチラシのほうが親近感を持たれやすいこともあります。 どのような仕上がりにしたいのかをイメージし、イメージに合わせてプロに依頼する、自分で撮るなど判断するとよいでしょう。
チラシの写真をスマホで撮影するときのコツ
プロに頼まず自分でもうまく写真を撮るには、どのようにしたらよいのでしょうか。スマホで写真を撮るときのコツをご紹介します。
昼間の自然光で撮る
明るい写真にしたいからとフラッシュを使って写真を撮ると、不自然に白浮きした仕上がりになってしまいます。 ナチュラルな雰囲気の写真を撮るには、昼間の自然光のもとで写真を撮りましょう。天気の良い日や明るい時間帯を選び、屋内で撮影するときは窓際など明るい場所を選んでください。直射日光を避けたいときは、レースカーテンがあると光が柔らかくなります。
背景に気をつける
オシャレな写真を撮ろうと、背景にあえて小道具を入れることがあります。しかしバランスを間違えると、ただ背景がごちゃごちゃした写真になってしまいます。写真の初心者であれば、なるべく背景には余計なものが写り込まないようにしたほうが無難です。商品の下にテーブルクロスを引くと、より商品が映える写真が撮れるのでおすすめです。
構図を意識する
プロのカメラマンは、必ずといっていいほど写真の構図を意識して撮影しています。写真の構図には3種類あり、被写体を中央に置く「日の丸構図」、上下・左右で画面を三分割した線上・交点上に被写体を置く「三分割構図」、画面中に三角形を作るように被写体を配置する「三角構図」があります。この構図を意識しながら、さまざまな距離やアングルで撮影し、ベストな一枚を見つけてみてください。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
補助金を活用しどのように集客アップにつなげたらよいかとお悩みの場合は、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。 チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。 ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ! 電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
クーポン付きチラシで集客力アップ!魅力的なクーポンの作り方
チラシにクーポンを付けると、チラシの反響率は高まる傾向にあります。しかしやり方を間違えると、せっかくのお得なクーポンも使われないままになってしまうケースも。お得感を分かりやすく伝え、集客力をアップさせるクーポンチラシの作り方を解説します!
クーポンを付ける目的とメリット
クーポンを付けることはお客さんとってはお得感があり喜ばしいことですが、お店側にとっては一時的に売上や収益が減少するといったデメリットがあります。
しかしクーポンを付けることにより来店・購入への動機になったり、客単価が上がったりするといったメリットにもつながります。
「気になってはいたけれど来店するきっかけがなかった」という人にとっては、クーポンで安くお得に購入することができることは、来店する後押しとなるでしょう。
また「ドリンク一杯無料」というクーポンがあれば、ランチやディナーのついでに使ってみよう、と来店しやすくなり客単価のアップも狙えます。
もし一度来店してもらい気に入ってもらえれば、クーポンがなくてもリピーターになってくれるかもしれません。また満足度が高かった場合は、さらに口コミ効果も期待できます。
そのためにもまずは、クーポンを活用し興味を持ってもらうことから始めましょう。
一目でクーポンだとわかるデザインになっているか
クーポン付きチラシの制作において重要なのは、チラシを見たときに一目で「クーポンが付いている」とわかるデザインになっていることです。
人はチラシを手に取ってから、ほんの数秒で「いる・いらない」を判断しています。クーポンが目立っていないと、そのわずかな時間ではクーポンに気が付いてもらえないことがあります。
ではどのようにしたら気づいてもらいやすくなるのでしょうか。クーポンを目立たせるには、いくつかのコツがあります。
まずはチラシの上部、特に左上に配置するとよいでしょう。人はチラシを読むときに、視線の動きが左上から右上、次に左下から右下というように「Z」の流れで読む習性があります。そのため真っ先に目に留まりやすい左上にクーポンを配置することで、お得な情報に気が付いてもらいやすくなります。
またクーポンを目立たせるには、色の使い方にも注意が必要です。チラシ全体のイメージをまとまったものにしたい、おしゃれな雰囲気にしたいなどの理由から、クーポンの色もチラシ全体と同じような色でまとめていませんか?
同系色でまとまったクーポンは目立ちにくく、見落とされてしまいます。クーポンの文字は大きく読みやすいフォントで、赤などの目立つ色でアピールしましょう。「クーポンを付けているのに反響がない……」とお困りの方は、一度チラシのデザインを見直してみてくださいね。
特典内容が一目でわかる内容になっているか
クーポン付きチラシにおいて、お得感が伝わりやすくなる言葉選びも大切です。
漢字のみを使った表現よりも、数字やカタカナを使った表現のほうが情報が伝わりやすくなります。
例えば「粗品進呈」よりも「無料プレゼント」と記載したほうが関心を引きやすく、「千円値引き」と記載するよりも、「1,000円オフ」としたほうが瞬時に情報を把握しやすくなります。
またプレゼントや特典の内容も、具体的にチラシに記載しておくことをおすすめします。プレゼントや特典が何なのかを記載しておくことで、読み手は自分にとってメリットがあるチラシなのかどうかを判断でき、行動に移しやすくなるでしょう。
クーポンに有効期限が載っているか
原則クーポンには、有効期限を記載することをおすすめします。「いつでも好きなタイミングで使ってもらえるように」と期日を設けないままにしておくと、せっかく興味を持ってくれているお客さんも「期日がないからいつでも行ける」と先延ばしになってしまうことがあります。期日が設定されていることで「○日までにいかなくては」と行動に移しやすくなり、来店を後押しする効果が期待できるでしょう。また期日が記載されていないチラシは、時間が経ったあともクーポンが有効であるかどうか分かりにくく、結局チラシが捨てられてしまうということもあります。 そのためクーポンの有効期限は必ず記載するようにしましょう。
クーポンを使うときに「めんどくさい」と思わせていないか
クーポンの使用方法はできるだけシンプルに、わかりやすくしましょう。
チラシについているクーポン部分を切り取って使用してもらうタイプのチラシも多くありますが、忙しい人などは切り取ること自体を手間に感じるので、チラシそのものを持参してもらうのも一つの手です。
一方で普段から大きなカバンを持ち歩く習慣がない人や、財布が小さくてチラシを入れられない人にとっては、チラシそのものを持ち歩くことは邪魔になってしまうことがあります。その場合はミシン線を入れて切り取りやすくするなど、ターゲットによってクーポンの使用方法を変えるとよいでしょう。
来店したいと思える魅力的なクーポンであるか
クーポンが付いているからといって、必ずしもお得感がでるとはかぎりません。そもそも大前提として、お客さんが新しいお店に行くには少なからずストレスや心のハードルを感じます。初めて行くお店への緊張や、期待通りのお店でなかったらどうしようといった不安感がある場合、「5%引き」といったクーポンではお得感が弱すぎてしまうケースがあります。
緊張や不安を上回るほどの魅力的なクーポン内容でなければ、お客さんの反応は薄いままスルーされてしまうでしょう。可能な範囲で、特典を充実させることを意識してみてください。
ターゲットに合った内容になっているか
クーポンの効果を最大限引き出すには、ターゲットをしっかりと設定することが重要です。まずは新規客向けなのか、既存客向けなのかを絞りましょう。
新規客向けであればお店のおすすめ商品を知ってもらいたいところ。「〇〇(看板商品)10%引き」といったクーポンをつけることで、どんな商品がウリなのか分かりやすく、安い価格で試してもらうことができます。
一方でリピーターを作るためのクーポンであれば、「2点購入するともう1点プレゼント!」といったように、買えば買うほどお得になる仕組みのクーポンにすると効果的です。
そしてチラシと同様、どんな人に使ってほしいクーポンなのかターゲットを絞りましょう。
「性別」「年齢」「クーポンを使うシーン」などを設定することで、クーポンの内容も変わってきます。
例えば男性の場合、新しい物やプラスアルファの商品よりも、分かりやすい定番商品を好む傾向にあります。「ラーメン一杯無料」や「いまなら25%増量」といったように、シンプルでわかりやすいクーポンがよいでしょう。
一方で女性の場合、新商品やいろいろな種類の商品を試すことを好む傾向があります。美容院で「トリートメント無料」や、レストランで「デザート無料」など、プラスアルファのクーポンに魅力を感じます。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
補助金を活用しどのように集客アップにつなげたらよいかとお悩みの場合は、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。 ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ! 電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
チラシ制作などの販促物に使える「小規模事業者持続化補助金」とは?
小規模事業者のなかには、販促活動にコストをかけられない、なるべく抑えたいと考える方も多いと思います。
しかし商品を知ってもらうには販促活動は必要不可欠です。そんなお困りの小規模事業者が受け取れる、「小規模事業者持続化補助金」を解説します。
チラシ制作に使える補助金とは
商品の売り上げアップを図るために、チラシの制作を検討している事業者も多いでしょう。そんなときにも、小規模事業者持続化補助金を活用することができます。
小規模事業者持続化補助金の申請にはさまざまな経費科目が設定されていますが、チラシを制作する場合は「広報費」に該当します。
チラシのデザイン料や印刷費用、ポスティング業者への発注費用など、チラシ制作にかかる経費を補助金によってまかなうことができ、上限額は通常枠で50万円、特別枠でインボイス特例要件を満たす場合は250万円の上限で補助を受けることができます。
小規模事業者持続化補助金特徴と申請方法
補助金にはさまざまな種類がありますが、小規模事業者持続化補助金にはどのような特徴があるのでしょうか。また補助金を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
小規模事業者補助金の概要
小規模事業者持続化補助金とは、従業員数や業種など一定の要件を満たした小規模事業者に対し、販路開拓や生産性向上などを目的とし支援するための制度です。
働き方改革やインボイス制度の導入、コロナによる影響など、世の中の情勢の変化により事業者はさまざまな経営課題に直面します。
なかには事業規模の小ささから資金に余裕がなく、経営危機に直面するケースも少なくありません。そんな小規模事業者が新たな販路を拡大し、安定的に経営を持続するために、一部の経費を補助する取り組みが小規模事業者持続化補助金制度です。
補助金の対象者
「小規模事業者持続化補助金の対象となる小規模事業者は、下記に該当する法人・個人事業・特定非営利活動法人となります。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員の数5人以下
宿泊業・娯楽業・・・常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他・・・常時使用する従業員の数20人以下
また補助金の対象者になるには、次の要件をすべて満たすことが必要になります。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること。
- 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと
(参照:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」補助金の対象者とは?)
補助対象となる経費
小規模事業者持続化補助金の申請では、経費の内容によっては補助の対象として認められないものがあるので注意が必要です。経費科目には次のようなものがあるので、事前に公募要領「5.補助対象経費」を確認しましょう。
- 機械装置等費(補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等)
- 広報費(新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等)
- ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費)
- 展示会等出展費(展示会・商談会の出展料等)
- 旅費(販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費)
- 開発費(新商品の試作品開発等に伴う経費)
- 資料購入費(補助事業に関連する資料・図書等)
- 雑役務費(補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用)
- 借料(機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
- 設備処分費(新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等)
- 委託・外注費(店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
補助金申請の手続き
小規模事業者持続化補助金申請の手続きは、「第○回公募」というように受付時期によってスケジュールが異なります。決められた受付締め切り期限内に、必要な申請書類を準備し提出しましょう。 受付締め切り後は審査を経て、採択決定者結果が公表されます。この補助金では要件を満たしたすべての事業者が補助金を受けられるわけではなく、審査の結果評価の高い順に採択者が決定されるので注意が必要です。
審査が終了すると補助金事務局ホームページにて、採択の結果が公表・通知されます。採択が決定した者は、応募時に提出した「補助金交付申請書」を事務局で確認したのち、不備等がなければ「交付決定通知書」が通知されます。
「交付決定通知書」を受領したあとは「補助事業計画」に沿って事業を実施し、定められた「補助事業実施期限」までに事業を完了させましょう。 事業完了後は補助事業の実施内容と経費の内容を記録した実績報告書を決められた先へ郵送します。最終締め切りまでに提出がないと補助金の支払ができなくなるので注意しましょう。
そして実績報告書と見積書などの証拠書類に基づき審査が行われ、補助金額が確定します。補助額が確定すると、「補助金確定通知書」が送付されるので、金額を確認し精算払請求を補助金事務局に行います。その後補助金が事業者の口座へ入金される流れです。
補助金が支払われたのち1年後には、「事業効果および賃金引上げ等状況報告」の提出も必要となるので忘れないようにしましょう。
どのくらいの補助が受けられるのかといった補助率や補助上限額は、通常枠や特別枠など自身が申請した内容により変動します。詳細は「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」をご確認ください。どのくらいの補助が受けられるのかといった補助率や補助上限額は、通常枠や特別枠など自身が申請した内容により変動します。詳細は「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」をご確認ください。
申請書類の準備と提出方法
申請者が法人、個人、NPOなどによっても、提出する書類に違いがあります。全申請者が提出すべき書類と、希望する申請者のみが追加で提出する資料があるので、事前に「応募時提出資料・様式集」を確認しましょう。万が一申請書類に不備があった場合は不採択となることがあるので注意が必要です。 提出方法は電子申請(補助金申請システム:Jグランツ)、または郵送によって受け付けています。窓口への直接の持参は不可なので注意しましょう。 また郵送の場合、商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるのでよく確認してください。
チラシを回収する
申請者が法人、個人、NPOなどによっても、提出する書類に違いがあります。全申請者が提出すべき書類と、希望する申請者のみが追加で提出する資料があるので、事前に「応募時提出資料・様式集」を確認しましょう。万が一申請書類に不備があった場合は不採択となることがあるので注意が必要です。
提出方法は電子申請(補助金申請システム:Jグランツ)、または郵送によって受け付けています。窓口への直接の持参は不可なので注意しましょう。 また郵送の場合、商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるのでよく確認してください。
チラシ制作に小規模事業者持続化補助金補助金を活用する際の注意点
チラシを制作する場合は、補助対象科目の「広報費」に該当します。商品やサービスのPRを目的としたチラシであれば補助金を受けることができますが、会社のPRや企業の営業活動に関するチラシは対象外となります。 そのほかにも商品やサービスの広報を目的としないパンフレットや看板、未配布のチラシなども対象外となります。 さらにチラシの配布が補助事業期間内にしていることも、補助金を受けるうえでの前提要件となります。 このように一言で「広報費」と言っても厳密な条件があるので、事前によく確認し注意しましょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
補助金を活用しどのように集客アップにつなげたらよいかとお悩みの場合は、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。 チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ! 電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
ポスティングが違法になることはある?クレーム対処法・予防策とは
ポスティング自体は違法ではない
ポスティングは住民に許可を取ることなくチラシを投函することから、勝手にやってよいのか、どこかに許可を取らなくてはならないのでは、と迷うこともあるでしょう。
結論からいうと、ポスティングをするにあたり住民や公共機関などへの許可や申請は必要ありません。またポスティングを取り締まる法律もないので、ポスティング自体は違法にはなりません。
しかしやり方を間違えるとクレームの原因になるだけでなく、警察に通報されたり、違法として訴えられたりしてしまうケースもあるので注意が必要です。
ポスティングが違法とみなされるケース
では具体的に、どのようなことをすると違法行為となってしまうのでしょうか。ポスティングをする際に知っておきたいポイントを解説します。
住居侵入罪
マンションやアパート、団地などの集合住宅では、チラシの投函を禁止している建物もあります。誤って投函してしまうとクレームにつながることもあるので、事前に管理人や管理会社に許可をとっておきましょう。事前に許可を取っていたにもかかわらず、住民によってはクレームがくることもあります。そんなときにも対応できるよう、管理人や管理会社から事前に「許可証」のようなものを書いておいてもらうと安心です。
住居侵入罪とは刑法第百三十条に定められており、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」という内容のものです。
ポイントは「正当な理由」があるかどうかですが、ポスティングはあくまでもチラシの企業側の都合であり、正当な理由として認められません。そのため居住者が望まない場合には、敷地内のポストに投函することは違法となってしまうので注意が必要です。
またマンションなどの集合住宅の場合では、エントランスや廊下などの共用部分も「住居」と判断されるので、念頭に置いておきましょう。
公序良俗に反したチラシを投函
アダルトビデオのチラシや風俗関係のチラシの投函は、違法となる可能性があります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二十八条第5項により、「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない」としてビラ等を頒布することを禁止しています。
またねずみ講の勧誘などの犯罪性のあるチラシ、人権侵害をするようなものは、自治体により迷惑防止条例に触れる可能性があります。
軽犯罪法違反
「投函禁止先の住居に誤って投函してしまった」などの理由から、一度投函したチラシを無断で取りだすと、軽犯罪法違反に該当する場合があります。そもそも投函ミスをしないことは大前提ですが、間違ってポスティングしてしまった場合でも、一度入れた投函物は取り戻そうとしないようにしましょう。
ポスティングは素人がやってはいけない?その理由は
ポスティングは販促活動として手軽で効果的な方法ですが、素人の判断のみでポスティングすることはおすすめできません。
先述したとおりポスティングはクレームも起きやすく、トラブルを避けるためには投函禁止先などの地域の情報、ポスティングに関するルールやマナー、法律や各自治体の条例における知識が必要となります。それらを勉強せずにクレームになってしまったとき、企業のイメージダウンやクレーム対応の労力など、損害は計り知れません。
そういったリスクを回避するためにも素人判断で行うのではなく、ポスティング業者に依頼すると安心でしょう。
ポスティングへのクレーム対処法
もしポスティングをした結果クレームに発展してしまった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。
誠心誠意、謝罪をする
ポスティングにクレームがきてしまった場合は、まずは誠心誠意謝罪をしましょう。仮にこちらに一切の非がなかったとしても、決して反論してはいけません。相手が不快に思っていることは事実なので、まずは謝罪をして相手に落ち着いてもらいましょう。
チラシを回収する
ポスティングしたチラシは即座に回収しましょう。チラシをそのまま放置してしまうと誠実さが伝わらず、さらなる怒りをかってしまう可能性があります。
今後はチラシを投函しないと伝える
しっかりと謝罪をしたあとは、今後一切チラシは投函しないことを相手に伝えます。また投函禁止の情報は配布スタッフ間で共有し、再発防止策を徹底しましょう。
金銭の要求には応じない
悪質な相手の場合、金銭を要求してくる場合があります。その場合にも慌てず、要求に応じないようにしましょう。誠心誠意話し合いを重ね、対話を図りましょう。
ポスティングのクレームにならないための予防策
ポスティングのクレームを未然に防ぐ為には、マナーを守った丁寧なポスティングを心がけることが大切です。そんなポスティングの際に気をつけたいポイントを解説します。
「チラシお断り」の張り紙がある住居を把握しておく
「チラシお断り」の表示がある住居の情報は、事前にチェックし把握しておきましょう。 古い住居の場合、張り紙の文字が薄れて見えにくくなっていたり、草木が茂り見えにくくなっていたりする場合があります。 また見えやすい位置に貼ってあるけれども投函者の注意力が散漫になっていて見落としてしまったり、暗い時間帯のため見落としてしまったりするケースもあります。 こういった投函ミスを防ぐために、ポスティング業者では投函禁止先をリストアップし情報を共有するなど、クレーム防止策を徹底しています。ポスティング業者でしか知りえない情報もあるので、あらかじめポスティング業者へ依頼すると安心でしょう。
雨や雪の日のポスティングを避ける
ポスティングは原則、雨や雪など天候が悪い日は避けましょう。雨などでチラシが濡れやすく、濡れてしわしわになったチラシは印象がよくありません。またポストを開ける際に雨水がポスト内に入り、すでに投函されている郵便物を濡らしてしまう可能性もあります。
雑なポスティングをしない
作業効率を意識するあまり、チラシを雑に投函しチラシが折れてしまったり、クシャクシャになってしまったりする場合があります。クシャクシャなチラシを投函された側としては、ゴミを入れられたように感じ不快に思う人もいます。投函する際は折れたり破れたりしないよう、丁寧さを心がけましょう。 また風が強い日はチラシをきちんと中まで入れないと、風で飛ばされてしまうことがあります。風で飛ばされ散乱したチラシは見た目が悪く印象がよくありません。クレームの原因にもなりやすいので、注意が必要です。
ポスティングで反響を獲得するなら、日本ポスティングセンターをお試しください
初めてのポスティングを検討している方や、どのような方法でポスティングしたらよいか迷っている方は、ぜひ一度日本ポスティングセンターへご相談ください。
日本ポスティングセンターでは研修を受けた自社の専属スタッフが配布しています。ポスティングのマナーを徹底し、過去の蓄積したデータや経験から、トラブルやクレームを未然に防ぐポスティングを行っております。
またスタッフにはGPS端末を持たせ、配布ルートの確認や不正を抑止する仕組みを採用。必要に応じて「GSP端末のデータ」も開示できるので、安心してご依頼いただけます。
また日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、ポスティングの投函方法をはじめ、チラシのキャッチコピーやデザインなど、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
この記事を読んで日本ポスティングセンターのポスティングに興味を持たれたなら、下記までお気軽にお問い合わせください。
ポスティングの単価や配布エリア、チラシ制作のご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
GW休暇のご連絡
平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心から御礼申し上げます。
当社では以下の期間をGW休暇とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
--------------------------------
4/27(土)~5/6(月)まで。5/7(火)から通常営業
期間中の4/27(土)4/30(火)5/1(水)5/2(木)については規模を縮小して営業しております。
--------------------------------
ご商談については恐れ入りますが
お休み明けより順次対応させていただきます。
※ポスティングご依頼中のお客様におかれましては
万が一クレーム等発生した際はメールにてご連絡下さい。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
2024.4.26
マナーを守ってポスティングを成功させるためのコツ
ポスティングは地域密着の集客や認知度アップに効果的な宣伝方法ですが、やり方を間違えるとクレームやトラブルの原因にもなりかねません。どんなことに気をつければよいのか、事前に知っておきたいポスティングのマナーについて解説します。
そもそもポスティングに許可は必要?
店舗の新規オープンやセールの告知など、ポスティングをしたいときに公的機関への申請や特別な手続きは必要なのでしょうか。
その答えとしては、ポスティングをするのに特別な許可や手続きは必要ありません。
誰でも自由に、必要なタイミングで行うことができます。しかし明確なルールや基準がないからこそ、人によっては迷惑行為として捉えられてしまったり、トラブルの原因になってしまったりすることも。そのためポスティングのマナーには、十分留意する必要があります。
ポスティングにおけるマナーとは?
ルールや法的な制約はないポスティングですが、どのようなマナーがあるのでしょうか。
まず大前提として、ポスティングはすべての居宅に投函可能なわけではありません。郵便物以外の物をポストに入れてほしくないなど、「チラシ投函禁止」の張り紙をしている居宅もあります。そういった投函禁止の住居に投函をしないことはもちろん、チラシを受け取った人に不快感を与えない内容や表現、投函方法に気を付けなければなりません。
注意すべきチラシの内容としては、政治や宗教に関する内容、またアダルト系のチラシは迷惑行為に該当する場合があります。
また投函時にクシャクシャにならないよう丁寧にポストに入れる、地域住民に不信感を与えないような時間帯や服装でポスティングをするといった、一般常識としてのマナーも存在します。ではどんなことに気をつければよいのか、次章では具体的なポスティングにおけるマナーをご紹介します。
ポスティングをする際のマナー
ポスティングのやり方を間違えると、ポスティングをした人だけではなく、チラシの広告主への印象も悪くなってしまいます。トラブルやクレームを未然に防ぐためにも、あらかじめ知っておくべきマナーを解説します。
管理人に交渉した後、配布する
マンションやアパート、団地などの集合住宅では、チラシの投函を禁止している建物もあります。誤って投函してしまうとクレームにつながることもあるので、事前に管理人や管理会社に許可をとっておきましょう。事前に許可を取っていたにもかかわらず、住民によってはクレームがくることもあります。そんなときにも対応できるよう、管理人や管理会社から事前に「許可証」のようなものを書いておいてもらうと安心です。
管理人・住人と顔をあわせたら挨拶をする
チラシの投函中に管理人や住人と顔を合わせたときは、気持ちの良い挨拶を心がけましょう。見知らぬ人がチラシを投函していること自体に不信感を持ち、快く思わない住人もいます。そのためなるべく明るい印象を与える挨拶を心がけましょう。
投函禁止のポストにはいれない
「チラシお断り」のような張り紙をしている居宅には、誤ってポスティングしないよう気をつけましょう。張り紙を見落としポスティングしてしまうとクレームにつながるだけでなく、敷地内のポストに投函すると住居侵入罪として問われる可能性があります。 古い住居などでは植木が伸び表示が隠れてしまっていたり、夕方や早朝など暗い時間の投函で表示を見落としてしまったり、張り紙そのものが薄くなっていたり剥がれてしまっているなど、目視しにくいケースもあるでしょう。そのため投函禁止先のデータを蓄積し情報を管理できている、ポスティング会社に委託すると安心です。
ポストからチラシがはみ出ないように投函する
ポストからチラシがはみ出していると、風で飛んでしまうなど景観を損ねる場合があります。地面に散らかったチラシは、地域住民に不快感を与えクレームの原因になってしまいます。また雨が降ったときにはみ出たチラシが濡れてしまい、ほかの郵便物まで濡らしてしまう可能性があります。投函するときは中までしっかり入れましょう。 しかし旅行など不在期間が長くポストがいっぱいになってしまっている場合は、無理にチラシを押し込むことはやめましょう。投函したチラシがクシャクシャになるだけでなく、ほかの郵便物も破けるなど破損してしまう可能性があります。
身だしなみに気を付ける
ポスティングをするときの服装は基本的に自由ですが、身だしなみが整っていないとポスティング業者だと思われなかったり、不審者とみなされてしまったりすることもあるでしょう。そのためポスティングをするときの身だしなみには十分気をつける必要があります。
第一に清潔感があり、ポスティング業者と分かりやすい格好を意識しましょう。
襟付きシャツやポロシャツは清潔感があり、きちんとした印象を与えます。色は明るいものを、柄はシンプルなものを選びましょう。服のサイズはダボっとしたものではなく、体形に合ったものを選ぶと好感を持たれやすくなります。
ポスティングの時間帯に気をつける
ポスティングをする時間帯は原則自由ですが、住民の迷惑にならない時間帯を選びましょう。深夜や早朝は人が少ないため、人がうろついているだけで住民に恐怖心や不安を与えます。そのため基本的に明るい時間帯に行うようにしましょう。一般的には、朝9時から夕方6時頃までに行うとよいでしょう。明るい時間帯に行うことで「投函禁止」の張り紙を見落としにくく、投函ミスなども予防できます。
雨や雪の日はポスティングしない
雨や雪など、天候が悪い日のポスティングは避けたほうがよいでしょう。チラシが濡れてしまうとチラシの印刷がにじんでしまったり、紙がふにゃふにゃになってしまったりと、受け取った側の印象がよくありません。また濡れたポストを開け閉めすることで雨露がポスト内に入り、すでに入っているほかの郵便物まで濡らしてしまう可能性があります。トラブルを未然に防ぐには、天気の良い日を選んでポスティングしましょう。
反響率アップのチラシなら、日本ポスティングセンターへご相談ください
初めてのポスティングを検討している方や、どんな方法でポスティングしたらよいか迷っている方は、ぜひ一度日本ポスティングセンターへご相談ください。
日本ポスティングセンターでは研修を受けた自社の専属スタッフが配布しています。ポスティングのマナーを徹底し、過去の蓄積したデータや経験から、トラブルやクレームを未然に防ぐポスティングを心がけています。
スタッフにはGPS端末を持たせ、配布ルートの確認や不正を抑止する仕組みを採用。必要に応じて「GSP端末のデータ」も開示できるので、安心してご依頼いただけます。
また日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、ポスティングの投函方法をはじめ、チラシのキャッチコピーやデザインなど、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
この記事を読んで日本ポスティングセンターのポスティングに興味を持たれたなら、下記までお気軽にお問い合わせください。
ポスティングの単価や配布エリア、チラシ制作のご提案まで、ご案内しています。
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
チラシの反響率をアップさせるペルソナ設定とは
チラシを使ったマーケティングにおいて、ペルソナという言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。ペルソナとは一体何なのか、どのように設定すればチラシの反響をアップさせるのかを解説します!
ペルソナとは何か?
そもそもペルソナとは何なのでしょうか?ペルソナとはマーケティング用語のひとつであり、顧客となる「架空の人物像」を設定することを指します。
「架空の人物像」というのは年齢や性別、職業や住んでいる場所など、あたかも本当にその人が実在しているかのように、具体的に人物像を絞り込んだものをいいます。
例えば「25歳女性で金融機関の事務の仕事をしており、都内で一人暮らしをしている」といった具合です。このように具体的な人物像を設定することで、その架空の人物の悩みやどのようなきっかけで自社の商品やサービスを購入するのかなど、より具体的な顧客のニーズや購入動機を把握することができるようになるのです。
チラシ作りにおけるペルソナ設定のメリット
ペルソナを設定することは見込み客のより深いニーズを把握できるだけでなく、魅力的なチラシを作るうえで重要な要素のひとつとなります。チラシ作りになぜペルソナ設定が必要なのか、取り入れるべき理由やメリットを解説します。
ユーザー目線でのマーケティングができる
チラシを作る際、ついつい企業側目線のおすすめ情報や商品の特徴ばかりを書いてしまいがちです。しかしお客様に「欲しい」と思ってもらうには、お客様の欲求にどう役立つのか、お客様目線に立った情報を意識しなければなりません。
ペルソナを設定することで自社の商品・サービスを客観的に見ることができ、どのようなアプローチをすればターゲットに刺さるのかをより深く想像することができます。
例えば美容院の宣伝において、ターゲットを20~30代の女性としていたとしましょう。しかしこれではターゲットの範囲が広すぎて、どのようにアプローチすればよいのかがぼんやりしてしまいます。
例えば「33歳女性の専業主婦で、2歳の子どもがいる。子どもがいるため美容にお金や時間をかける余裕がない」というペルソナ設定をしていた場合、よりリーズナブルなメニュー設定で、時間がないなか予約がとりやすいこと、スピーディーに施術が終わることなどがアピールポイントになるでしょう。同じ33歳女性でも「独身でフルタイム勤務」のペルソナであれば、時間やお金にも余裕があることが想像されます。そのため多少高価であっても豊富なメニューの提案や、休日にゆっくりとした癒しの時間を提供できることをアピールするほうが来店してもらいやすくなるかもしれません。
このようにペルソナ設定の仕方によって、見込み客へのアプローチ方法は全く変わります。ユーザー目線に立ったマーケティングをするうえで、ペルソナ設定は重要です。
社内における情報認識の共有がしやすい
ペルソナ設定のメリットは、顧客へのアプローチだけではありません。社内においてどのようなマーケティングを展開するかにおいても、効率化を図ることができます。
一般的にマーケティングをする際、複数の部署や担当者によって戦略が練られるケースが多いことでしょう。しかしその関係者一人ひとりの描くターゲット像にずれがあると、社内ミーティングでも効率的に話し合いが進まなかったり、いちいち認識をすり合わせなくてはならなかったりと手間がかかります。
しかしあらかじめ詳細なペルソナを設定しておくことで、社内一人ひとりが情報の認識を共有しやすく、マーケティング戦略の立案もスムーズに進めることができるでしょう。
時間とコストを削減できる
ペルソナ設定をしていると、時間とコストを削減できるというメリットもあります。見込み客の詳細な情報が明確になっているので、マーケティング戦略の決定もスムーズに展開し、ミーティングなどにかける時間の削減につながるでしょう。
またピンポイントにターゲットにアプローチできるので、無駄な販促物が発生することもなく、集客コストの削減なども期待できます。
チラシ作りのペルソナ設定の手順
ではいざペルソナを設定するとき、どのような手順で進めたらよいのでしょうか。チラシ作りにおける段取りを解説します。
1.必要な情報を集める
ペルソナ設定では、闇雲に架空の人物像を設定してよいわけではありません。まずはペルソナの基となる顧客の性別や年齢、職業、商品の購入動機や目的などをリサーチするため、事実に基づいた情報を収集します。
例えば過去の販促実績情報や顧客へのアンケートやインタビュー、社内の聞き取り調査や社内の分析データ、SNSでの反応調査や公的機関が公開している調査結果などを収集することで、ペルソナの条件設定に活かせるでしょう。
2.情報を整理し、人物像を組み立てる
情報が集まったら内容を整理・精査し、人物像を組み立てていきます。ペルソナ設定に必要となる情報は、主に次のような内容になります。
- 名前
- 年齢
- 性別
- 居住地
- 職業
- 勤務地の場所
- 年収
- ライフスタイル(起床・就寝時間、空いた時間の過ごし方、出社・帰宅時間など)
- 性格
- 趣味
- 家族構成
- 休日の過ごし方
- 悩みや欲求
このように第三者でもイメージできるほどに、詳細なパーソナル情報を設定しましょう。ライフスタイルなどを細かく設定することで、その環境や状況に近いターゲットに対し、より深く刺さる言葉選びや販促活動ができるようになります。
チラシ作りのペルソナ設定で注意すべきポイント
チラシ作りのペルソナ設定において、注意すべきポイントがあります。具体的にどんなところに気をつけたらよいのかを解説します。
自社の理想像にしない
ペルソナ設定では、自社目線に傾かないように気をつけましょう。自社にとって都合のよい情報ばかりを参考にしたり、企業にとって都合のよい顧客像にしてしまったりなど、客観性を欠いたペルソナは実際の顧客のニーズからかけ離れてしまいます。顧客のニーズを正しく把握できないままチラシを配っても、ターゲットに刺さらないだけでなく、かけたコストも無駄になってしまうでしょう。ペルソナは自社の理想像にせず、あくまでも事実に基づいた内容を意識しましょう。
定期的な見直しが必要
顧客のニーズやトレンド、社会情勢は常に変化していきます。そのためペルソナも、定期的に見直す必要があります。「顧客はいま何に悩み、何を必要としているのか」を把握する姿勢を忘れず、最新の情報に更新していきましょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
ペルソナ設定がしっかりできていることは、チラシの訴求率をアップさせ、よりターゲットに刺さるチラシとなります。その結果、集客効果も上がるでしょう。
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「どのようにペルソナを設定したらよいのか」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
その他、ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
集客効果のあるポスティングチラシを作るなら「コピーライティング」を押さえよう!
読まれるチラシを作るには、心を動かすコピーライティングが必要不可欠です。しかしどのようにしたら、ターゲットに刺さるコピーを作れるのでしょうか。コピーライティングで意識するポイントや、集客効果を高めるコツを解説します。
チラシ制作に重要な「コピーライティング」とは?
コピーライティングとは、商品の購買を促すことを目的とした文章のことを指します。ただ商品の魅力を紹介するだけではなく、お客様に「欲しい」と思ってもらうための人間の行動心理を組み込んだ文章でもあります。読み手の感情に訴えながら購買意欲を刺激するので、マーケティング戦略としても非常に重要となっています。
コピーライティングは購買行動を促すだけでなく、企業のブランドイメージの構築や情報提供、宣伝広告の役割も果たします。
そんなコピーライティングは、次の4つの要素から構成されています。
1.キャッチコピー
ターゲットの興味関心を引くうたい文句のことです。商品の特徴を端的に分かりやすく伝えるだけでなく、商品の印象を左右し、売り上げにも影響を与える重要なものです。キャッチコピーはチラシにおけるタイトルそのもの。ここでお客様の興味を引き、ワクワクドキドキを喚起することができれば、最後までチラシを読んでもらう可能性は高まるでしょう。一方ここでお客様の関心を引くことができなければ、チラシ自体読んでもらうことは難しいとも言えます。
ボディーコピー
ボディーコピーとは、商品の詳細のことです。商品の特徴を紹介し、購入することでどのような満足感や利便性が得られるのかを伝えます。さらにお客様の信頼や共感を得る役割もあるため、体験者の口コミなど客観的な情報を取り入れることで、より説得力をもたせることができます。
クロージングコピー
せっかく興味を持ってもらえても、購入に至らないと意味がありません。ターゲットが行動に移しやすくなるような文章を、クロージングコピーといいます。例えば「先着○名様」、「今だけ○割引」など、希少性を訴える文言が挙げられます。
コピーライティングで重要なのは、誰に訴えかけたいのか、ターゲットの悩みや課題は何なのか、悩みや課題を解決するためにどのようなベネフィットを提供できるのかをはっきりとさせることです。そのためには自社製品の強みをしっかりと分析することも欠かせません。そういった要素を踏まえ言葉に乗せることで、初めて人の心を動かすコピーライティングとなるでしょう。
チラシ制作における「コピーライティング」の5つのポイント
キャッチコピーを作ってみたものの、本当にターゲットの関心を引くコピーライティングになっているのか、不安に思われる方も多くいると思います。コピーライティングではどのようなことを意識すればよいのか、より印象に残りやすくする5つのポイントを解説します。
ターゲットに合う言葉を使う
チラシを制作する上で、ターゲットの目線を意識することは非常に重要です。ターゲットが慣れ親しんでいない言い回しや世界観では、「自分とは関係のない情報だ」と無意識のうちに判断され、読まれにくいチラシなってしまいます。性別や年齢ごとにターゲットに合う言葉を選ぶとよいでしょう。
男性向け
男性向けのコピーライティングでは、「~だ」「~である」といった言い切り型の表現方法が好まれます。命令形や専門用語にも抵抗がなく、むしろ自分の知らない専門用語に対しては興味を抱く傾向があります。また製品の性能や仕様といったスペック表示を好む傾向があり、データやロジックを織り交ぜた論理的でストレートな言葉が刺さりやすいでしょう。一方で擬音語や擬態語のような抽象的な表現は好まれないため避けましょう。
10代~20代向け
10代~20代といった若い世代に向けては、友達のようなカジュアルな表現方法が好まれます。漢字が多すぎる、堅苦しい言葉を使うことは抵抗感が強まるので、固い表現になりすぎないよう注意しましょう。また「僕ら」「みんなで」といった、横のつながりを意識させる言葉を取り入れるのも効果的。友達とのつながりを重視するこの世代ならではの特徴であり、自分事として捉えてもらいやすくなります。ほかにも「めっちゃ」「ヤバイ」など、10代~20代の日常会話に出てくるワードを織り交ぜると、共感や親近感を持たれやすくなり関心を引くでしょう。
30代~40代向け
30代~40代になると、これまでの若い時代に好んでいたカジュアルなものとは一味違う、洗練された上品さに魅力を感じるようになります。そのため「上質な~」「ワンランク上の~」など、「大人っぽさ」を感じさせる言葉が刺さりやすくなるでしょう。
またこの世代はこれまでとは違うこだわりを発見し、自分らしい生き方に磨きをかけるなど、自分らしいスタイルを追求する傾向にあります。そのため「新定番」や「~空間」、「私らしい」といった言葉が好まれるでしょう。
シニア向け
シニアと一言で言っても、60代と90代ではまったく感性が異なるでしょう。近年のシニア層は若々しい人も多く、年寄り扱いをすることを嫌う傾向にあります。「いつまでも若々しくいたい」という願望に寄り添った、「新シニア世代」「人生を楽しむ」などのフレッシュな言葉を好むでしょう。
またこの世代はカタカナや英語が得意ではありません。専門用語などを避け、なるべく日本語で解説すると抵抗がなく受け入れやすくなります。
一方で尊敬語や丁寧語などかしこまった表現は、「格式が高い」「きちんとしている」ものとして好まれる傾向にあります。イメージ先行型の抽象的な表現や、インパクト重視の尖った過激な表現には抵抗感が強いので避けたほうがよいでしょう。情報は分かりやすく、端的な表現がおすすめです。
数字や比較を使った具体的な表現をする
コピーライティングでは、数字や比較を取り入れた表現が大切です。例えば「9割のお客様がリピートする~」、「50代女性のための~」など、数字が入ることで情報が具体的になり、説得力が増します。
また比較を使った表現方法では、現状に不満を感じている人に対して効果的です。例えば「体重が10キロマイナスに」、「偏差値が20上がる」など、現在と比較しこれからの明るい未来をイメージさせることができます。数字が入ることでよりイメージしやすくなり、ワクワクの喚起や期待値を高める効果があるでしょう。
書き出しで読者のベネフィットを伝える
人は文章を読むことに、多少なりともストレスを感じます。なかなか結論のでない文章は、誰でも読む気を失ってしまうでしょう。それはポストに入っているチラシに対しても、同じことが言えます。
人はチラシを手に取ったとき、瞬時に「いる・いらない」を判断しています。そのため読んでもらうためには、書き出しでその商品がどのようなベネフィットがあるのかを明示する必要があります。
冒頭で「この商品ではこのようなことが叶えます」「誰でもこんな自分になれます」というベネフィットを伝えることで、ターゲットのワクワクや好奇心が刺激されます。
このように読み手の知りたい情報を最初に伝えることで関心を引き、離脱せず最後まで文章を読んでもらいやすくなるでしょう。
小見出しを効果的に使う
コピーライティングでは、小見出しを上手に使うことで情報を伝えやすくすることができます。小見出しとは文章の内容ごとにタイトルをつけることを言います。特にチラシにおいては、ほんの数秒で捨てるかどうかを判断されています。そのためパッと見ただけで内容が伝わるような見出しの工夫が必要です。伝えたい情報を整理し、キーワードを織り込んだ端的な表現を心がけましょう。フォントや文字のサイズに緩急をつけると、読みやすくなります。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
「どんなキャッチコピーを作ったらよいのだろうか」と迷ったら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるコピーライティングのお手伝いをいたします。
またコピーライティングだけではなく、チラシのデザインやポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」はおまかせください。
その他、ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
DTPデザインとは?チラシ制作における重要性
ポスティングチラシを制作するときに、「DPTデザイン」という言葉を初めて聞く人もいるかもしれません。印刷・出版業界では知られている「DPTデザイン」ですが、どのようなものなのか、チラシ作成にどのような影響があるのかなどを解説します。
そもそもDTPデザインとは?
DPTとは「Desk Top Publishing」の略で、DTPデザインとはパソコン上でデザインを調整し、印刷物データを制作できるレイアウト専用ソフトのことです。例えば使用するイラストや写真を見やすくなるよう配置したり、フォントの種類や大きさを調整したり、色や全体の印象を確認したりすることができます。主にチラシやポスター、パンフレットなど、紙媒体の制作物をデザインする際に使われています。
DPTデザインが普及する1980年以前は、デザインや版下作成、製版や印刷がそれぞれ分業で行われていました。まずデザインを担当するデザイナーが文言や写真の入った版下とよばれる原稿を作成していました。
版下が仕上がると印刷会社が紙面に出力し、そこで初めてデザインイメージを確認することができます。しかしお客様のイメージと相違した場合は再度イメージのすり合わせを行い、何度も版下を制作しなければならないこともありました。そのため時間やコストがかかってしまい、非効率な点が問題となっていました。
しかしDPTデザインが普及したのちは、レイアウトから印刷後のイメージ確認まで一人のデザイナーがパソコン上で進めることができるようになり、大幅に制作効率が改善されるようになったのです。
チラシのDTPデザイン 「CMYK」と「 RGB」の違い
とても便利で使い勝手のよいDPTデザインですが、実際に紙に印刷された際の仕上がりがイメージと異なる場合があります。特にDPTデザインにおける色の表現方法には「CMYK」と「 RGB 」があり、それぞれ特徴が異なるので注意が必要です。「CMYK」と「 RGB 」とは何なのか、それぞれの違いを解説します。
「CMYK」
CMYKとはインクを使用して色を表現する方法です。「C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)」の3色を使用し、紙などの印刷物における表現に使われます。CMYは「色の三原色」と呼ばれ、反射によって色を認識しますが、混ぜるほどに黒に近くなるため「減法混色(減法混合)」とも呼ばれます。実際にはこの3色ではキレイな黒が再現できないため、K(キープレート)を加えたCMYKとなっています。
RGBと比較すると鮮やかな色を表現することは難しく、RGBからCMYKに変換すると少しくすんだ色味になるので注意しましょう。
「RGB」
RGBとはパソコンやスマートフォン、テレビの画面などにおける色の再現方法です。「R(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)」の3色の組み合わせにより、さまざまな色を画面上で表現することができます。RGBの3色は「光の三原色」と言われ、発光によって数多くの色を再現しています。色を混ぜるほどに白色に近づくので、「加法混色(加法混合)」と呼ばれています。
しかし一方で、画面を見る環境によって異なる色に見えてしまうことがあるというデメリットも。部屋の明るさやディスプレイの性能などにより、見え方に差が出ることがあるので注意が必要です。
チラシ制作におけるDTPデザインの重要性
チラシ作成をする際のDTPデザインでは、先ほど解説した色の表現方法の違いがあるので印刷が仕上がりに注意する必要があります。
例えばWEBデザインとDTPデザインを比較してみましょう。
WEBデザインでは、いつでもWEB上でデザインを修正することができ、載せる情報量にも制限がありません。コンテンツの追加やバナー広告の差し替えなどのアップデートも簡単に行うことができます。しかし見る側の環境(ブラウザや媒体、部屋の明るさなど)によっては色や印象に差がでる場合があるので、伝えたいイメージを一律に伝えることが難しいケースもあります。
一方DTPデザインでは、最終的に紙に印刷する工程があります。印刷後は修正ができないので、より色の選び方や印刷する紙質の選定には慎重になる必要があります。
しかし印刷し完成したあとは、デザインの印象は見る側にとって差はありません。それは紙媒体の強みでもあり、伝えたいイメージを誰にでも等しく伝えることができるというメリットでもあります。ポスティングチラシを作成する際にも、伝えたいイメージがばらつきなく伝えることができるのは大きな利点となるでしょう。
DTPデザインを使った読みやすいチラシ制作のポイント
DTPデザインを使用してチラシを作成する際に、どんなところに気をつければよいのかをご紹介します。ポイントを押さえ、読んでもらいやすいチラシ作りを目指しましょう。
ペルソナを設定する
読まれるチラシ作りをするには、まずそのチラシは誰に読んでもらいたいのか、詳細なペルソナを設定しましょう。
年齢や性別はもちろん、家族構成や職業、趣味嗜好や悩んでいることなど、より具体的な条件を抽出しターゲットとなる人物像を設定します。
アプローチするターゲット像が明確になることで、どのような文言や写真、色の選び方やレイアウトにすればよいのかなど、デザインの方向性がより明確になるでしょう。
刺さるキャッチコピー
ターゲットが明確になったら、そのターゲットに刺さるキャッチコピーを考えましょう。
読み手が思わず惹きつけられるキャッチコピーとは、共感できることが大切です。自分と同じような悩みを持つ人が悩みを解決できている、自分が抱える課題の解決策が提示されている、自分では気が付かなかった欲求を満たすことができる方法が記載されているなど、読み手がどのようなベネフィットを得られるのかを分かりやすく伝えるキャッチコピーを目指しましょう。「リピート率90%の~」「50代のための~」など、具体的な数字を組み込むとより説得力のあるキャッチコピーになります。
見出しの文字サイズを調整する
見出しの文字を大きくし、目立たせるという作業は日常でも行っているかと思います。チラシ制作においても文字サイズを調整することは、チラシを見やすく、内容を瞬時に伝わりやすくするうえで必要な工程です。
文字サイズの調整はチラシを読みやすくするだけでなく、レイアウト全体から受ける印象も操作することができます。
週刊誌など話題性を目立たせたい場合は極端に文字を大きくし、インパクトを強調します。そうすることで躍動感や世俗的さ、衝撃的な印象を与えることができます。
一方教科書や公式な文書などの見出しは、大きすぎずまとめることが多くなっています。大きくしすぎないことで気品や上品さ、信頼性を持たせることができます。
このように、読み手にどのような印象を与えたいかによっても、文字サイズを調整するとよいでしょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
反響があるチラシには法則が存在します。
ポスティングをしてもチラシの反響が感じられていない場合、もしかしたらチラシのデザインやレイアウトに原因があるのかもしれません。
自社のチラシが「本当にこれでいいのだろうか?」「どのようにしたら反響が出るのだろうか?」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターへご相談ください。
これまで培ったノウハウを踏まえ、的確にアドバイスいたします。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら
0120-062-206